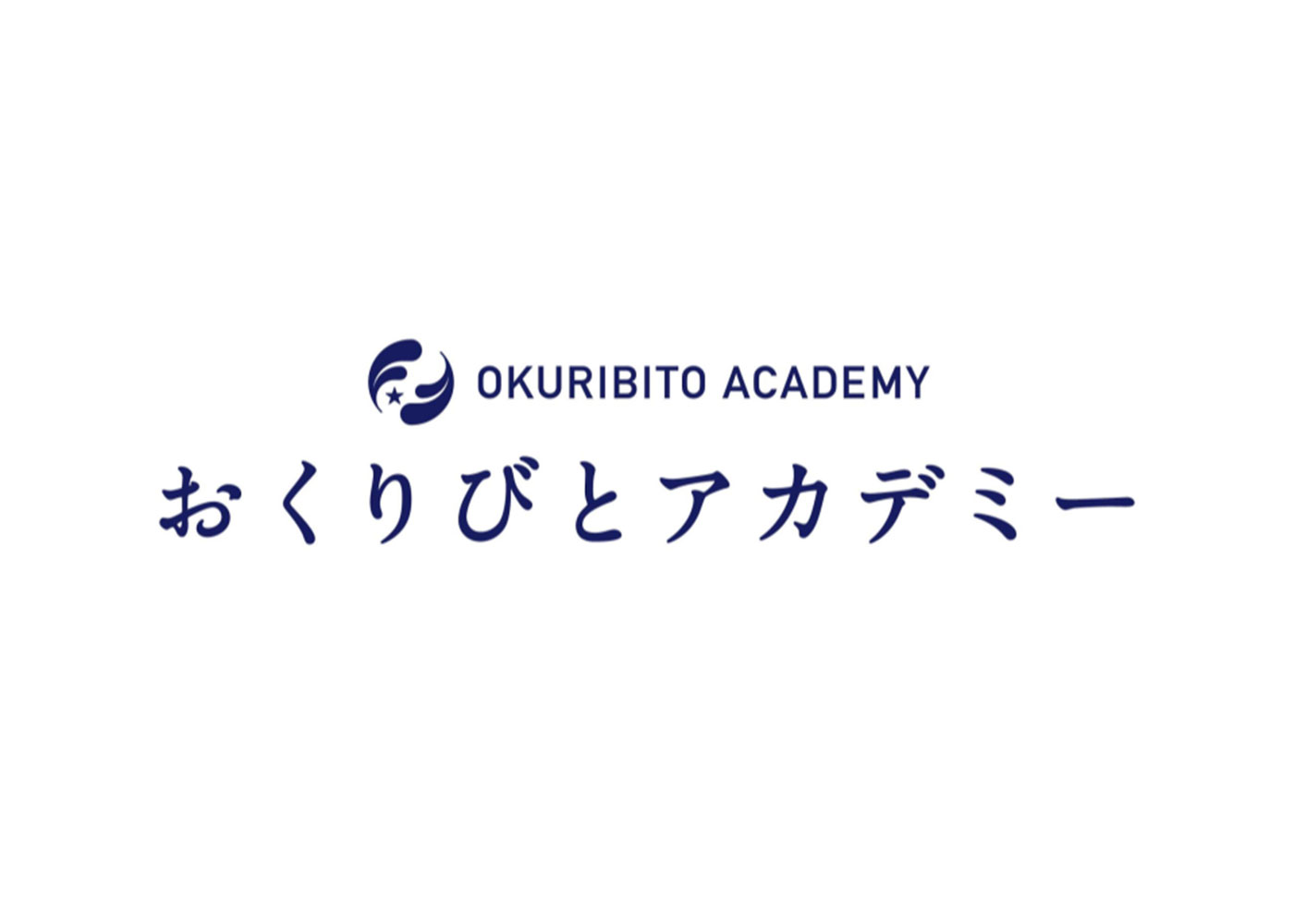こんにちは!次世代死生観研究所(仮)研究員のおおはしです!
前回はグリーフケアについてまとめましたが、
「ケア」繋がりということで、今回は「エンゼルケア」について調べてみました。
そもそもエンゼルケアって、何?
そもそもエンゼルケアって何をするのでしょうか?
グリーフケアと比べると、最近聞くことも増えてきたのではないかと思いますが、同じ「ケア」でも中身は全くの別物です。
特に医療関係の方は、実際に行なったことのある方もいるのではないでしょうか。
エンゼルケアとは、ご遺体に対して行うメイクや清拭、お着せ替えなど、生前の姿に近づける処置全般を指します。
似たような言葉で、「湯灌」や「エンバーミング」などもありますが、湯灌は儀式色が強く、決まった順番や作法があり、エンバーミングは遺体を綺麗な状態で長期的に保存することが目的です。
順番に詳しく解説していきます。
「湯灌」との違い
湯灌は、暖かいお湯やぬるま湯で故人様のお身体を拭いて差し上げることを言います。
温めることで死後硬直を和らげ、棺に納めやすくする、生前の苦しみや穢れを洗い流す、という意味もあるようです。
湯灌は昔から行われてきたため、儀式的な側面も強く持ちます。
例えば、「目隠しや人払いを行い、立ち合いは近親者のみで行う」といった部分や、「身体を清める儀式」という部分が強いのが特徴です。
エンゼルケアでも清拭(アルコールを含ませた綿で身体を綺麗にすること)をしますが、
近親者が部屋に入る前に病室で済ませてしまうこともよくあります。
また、エンゼルケアは生前の姿に近づけることを目的としているため、身体を清めるといった意図は持たないのが大きな違いと言えます。
「エンバーミング」との違い
エンバーミングとは、薬剤を用いてご遺体の長期保存を可能にすることを言います。
通常はドライアイスや専用の霊安室を使用しても、2~3日か長くても1週間程度しかご遺体を安置することができませんが、エンバーミング処置をすることで最大50日程度ご遺体を保存しておくことができるようになります。
そのため、遠方から参列者がいらっしゃる場合や、ご遺族や参列者のスケジュールが合わない、火葬場が空いていない…などの際に利用されるケースがよく見られます。
ただし、エンバーミングをするには日本遺体衛生保全協会(IFSA)に認められたエンバーマーの資格が必要です。また、専用の処置室がある場所も限られており、専門的な技術が必要になるため費用も15〜30万円と高額になりがちです。
また、ご遺体にメスを入れたり、薬剤を入れたりすることに嫌悪感を抱くご遺族も多いと聞きます。
では、ドライアイスで安置するのと何が違うの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ドライアイスで安置をする場合、ドライアイス代と交換費用を含め、1日あたり8,000〜10,000円ほどかかることが多いので、2週間以上の安置が必要になるのであれば、エンバーミングをする方が費用を抑えられる場合があります。
さらに、ドライアイスは長期間身体の上に置いておくと、ご遺体が黒ずんでしまう原因にもなります。
その点、エンバーミングを依頼すると、ご遺体を綺麗に修復して生前の姿に近づけることもできますし、感染症などのリスクから守って安全に面会をすることができます。
安置の日数にもよりますが、同じくらいの金額になるのであれば、エンバーミングを依頼することも検討しておくと良いかもしれません。
エンゼルケアもご遺体の状態を生前に近づけるという部分では似ていますが、長期保存に特化しているのがエンバーミング、お亡くなり直後に看護師や納棺士が一時的にご遺体の状態を整えるのがエンゼルケア、という認識でもいいと思います。
エンゼルケアの流れ
では、実際にエンゼルケアが行われる流れを見ていきましょう。
(ここでは、病室で看護師が行うエンゼルケアの一般的な流れを記載いたします。
施設によって順番や方法が違う場合もありますので、ご了承ください。)
① 医療器具の取り外し
治療に使用していた点滴、ドレーンチューブ、人工呼吸器などの医療器具を外します。
血管カテーテルは出血防止のため、そのままにする場合もあります。
ペースメーカーを装着されている場合は、火葬時に爆発する恐れがあるため、事前に取り外します。
② 傷や体液の処置
治療痕や傷は、ガーゼなどで覆い目立たないように整えます。
体内に体液が残っているとご遺体の腐敗が急速に進んでしまい、感染症のリスクも上がってしまいます。
そのため、体液を排出する必要があります。
場合によっては紙おむつを装着し、周囲が汚れないように配慮します。
③ 口腔ケアと口の閉鎖
口腔内を清拭し、歯ブラシやガーゼ、アルコールで清潔に整えます。
喉の奥には消毒液を染み込ませた綿を詰め、体内から上がる臭気を抑えます。
口は死後硬直が解けると自然に開くため、顎の下にタオルを置き枕の角度を調整して閉口させます。
④ 全身の清拭(せいしき)
温かいタオルやアルコール綿で全身を拭き、皮膚の汚れを取り除きます。
皮膚を傷つけないよう丁寧に行い、清拭後は保湿ローションを塗布して乾燥を防ぎます。
肛門や鼻腔、耳孔には脱脂綿や専用ジェルを詰め、体液の漏出を防ぐこともあります。
ご希望があれば、ご家族による清拭も可能です。
⑤ 着替え
衣服は、病院で用意された浴衣や白装束のほか、生前に愛用していた服や宗教・宗派に沿った服を着せることもできます。
死後硬直が進むと着替えが困難になるため、着やすい衣服を選ぶことが望ましいです。
浴衣の場合は「襟は左前」「帯は縦結び」の日本の慣習に従って着付けます。
下着の代わりに紙おむつを使用します。
⑥ 容姿の整え(死化粧・エンゼルメイク)
お顔を生前の穏やかな表情に近づけるため、死化粧(エンゼルメイク)を行います。
肌は乳液で整え、男性は髭を剃ります。温かいタオルで顔を温め、シェービングフォームや石鹸で泡を作り、電気カミソリで丁寧に剃ります。
化粧は肌色や故人さまの好みに合わせ、男性でも自然な表情になるよう軽く施します。
口紅を避けたい場合はリップクリームやワセリンで代用します。
髪はドライシャンプーやリンスで整え、櫛で丁寧にとかします。
ウィッグやヘアピース、髪飾りを使用する場合は、事前に準備しておきます。
搬送時に腕が垂れないよう、「合掌バンド」で胸の上で手を固定する場合があります。
安置後は手のむくみや変色を防ぐため、速やかに外します。
最近では、腕を横に置く形で安置するケースも増えています。
⑦ 白布をかける
処置がすべて終わったら、体をシーツで覆い、顔に白布をかけます。
ご希望に応じて、顔を見える状態のまま安置することも可能です。
最後に胸の上で手を組ませて合掌させ、全身をシーツで覆ってエンゼルケアは完了です。
エンゼルケアはなぜ必要なのか?
エンゼルケアをはじめ、湯灌やエンバーミングなどのご遺体を綺麗に保つ処置は、故人様の尊厳を守り、ご遺族が穏やかな気持ちでお別れできるようにサポートする役割があります。
故人様の尊厳を守る
例えば病院でお亡くなりの場合、医療機器が挿入されていることが多くあります。また、自宅でお亡くなりの場合でも、長期間お風呂に入れなかったり、衣類が汚れてしまっていたりすることがあります。
エンゼルケアで機器を外し、身体を綺麗にして生前の姿に近づけることで、最期まで故人様の尊厳を守ることができます。
ご遺族のグリーフを和らげる
前回の記事にもあった「グリーフケア」にも繋がることですが、故人様は闘病や事故などで生前の姿と状態が変わってしまっていることが多いです。
ご家族が故人様と対面したときに感じる深い悲しみを和らげ、また生前の姿に近づけることで、
ご家族に「最後まできちんと見送ってあげられた」と納得してお別れをしていただくために、エンゼルケアを行うことが必要とされています。
おわりに
今回はエンゼルケアについてまとめてみました。
同じ「ケア」でも、グリーフケアとエンゼルケアでは目的や方法が全然違うということがわかりましたね!
調べてみると意外と奥が深く、まだまだ書ききれないこともたくさんありましたので、ぜひご自身でも調べてみていただきたいです!
今度はエンバーミングについても記事にしたいと思っていますので、続報をお待ちいただければと思います。