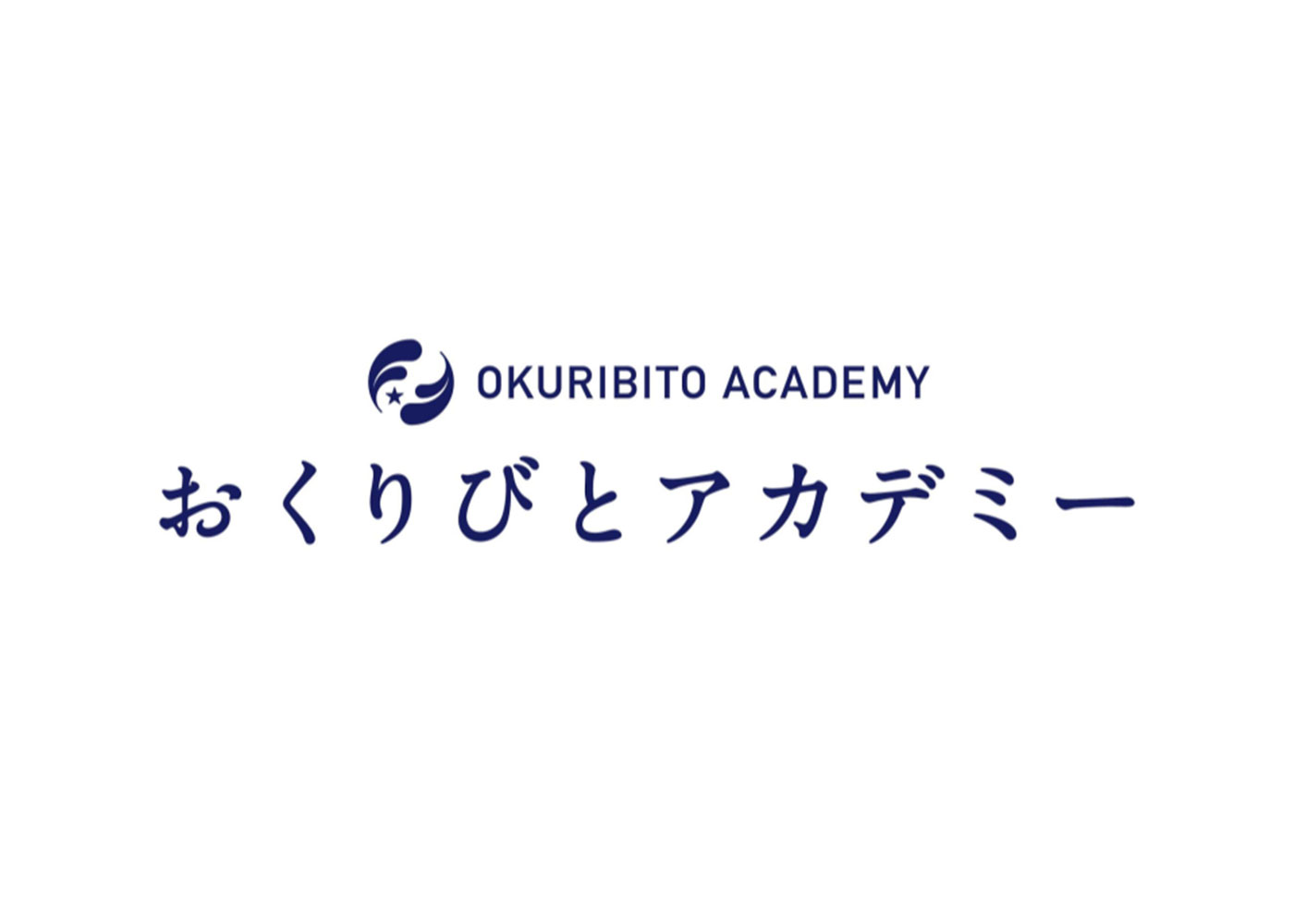こんにちは。
次世代死生観研究所(仮)の、たくやと申します。
本日は、納棺師という職業について、解説していきます。
納棺師とは?
納棺師(のうかんし)とは、亡くなられた方を棺に納める前に、身なりを整え、旅立ちの支度をする専門職で、主に葬儀中に行われる「納棺の儀」を執り行います。
ご遺体を清め、衣服を整え、髪や顔を美しく仕上げることで、ご遺族が安心して故人様とお別れできるように支えます。
近年では映画の影響もあり、「おくりびと」と呼ばれることもあり、日本独自の葬送文化に深く関わる仕事です。
納棺師が出てくるメディアは?
納棺師という職業が広く知られるようになった大きなきっかけは、2008年に公開された映画『おくりびと』です。
納棺師を題材にしたこの映画は、日本アカデミー賞のみならず、米アカデミー賞外国語映画賞も受賞し、世界的に注目を集めました。
近年では、2026年公開予定の「ほどなく、お別れです」という映画があります。
予告編では、劇中で葬祭プランナーを演じるSnow Manの目黒蓮さんが「納棺の儀」を執り行う映像が公開されました。
また、小説現代長編新人賞を受賞した『アフターブルー』という小説も、納棺師を描いた作品です。
納棺師の仕事内容は?
納棺師の主な仕事は、「納棺の儀」と呼ばれる儀礼を行うことです。
身体を洗い清め、衣服のお着せ替えをし、死化粧、髪を整えるなど、亡くなった方が安らかな表情で旅立てるように準備します。
ご遺族が立ち会う中で進められることも多く、ご遺族の心の整理を助ける役割も大きいのが特徴です。
技術的な面に加えて、丁寧な所作や心配りが欠かせません。
「納棺の儀」を通して、ご遺族が故人様としっかりと向き合うことができる時間を作り出します。
「納棺の儀」の流れ
納棺の儀とは、故人様の新たな世界への旅立ちが安らかであるよう祈りながら、身支度を整えた故人様をお棺に納め、副葬品を納めるまでの一連の儀式のことをいいます。
流れや作法は、地域や状況,、宗派によって内容が異なる場合があるため注意が必要です。
末期 (まつご) の水
故人様の口元を水で湿らす葬儀での最初の儀式です。
喪主を筆頭とする故人様と血縁が近い方から順番に、枕元に近づき、箸の先につけた脱脂綿や筆、または菊の葉や樒(しきみ)などを水に浸してから故人様の口元を湿らせます。
清拭(せいしき)
清拭とは、故人様の体をきれいに拭いて清める儀式です。
生前の労をねぎらい、穢れを落とす意味があります。
家族が立ち会い、感謝とお別れの気持ちを込めて行われます。
お着せ替え
本来ですと納棺の儀式を仏式で行う場合、浄土への旅の身支度として、安置の際に着ていた浴衣やパジャマから死装束へ着せ替えをします。
近年では、生前故人様がお好きだったお洋服や、ご家族の思い入れのある衣類にお着せ替えすることも多いです。
死化粧
死化粧は現代では「エンゼルメイク」とも呼ばれることもあります。
一般的には髪型や身なりを整え、必要であれば爪を切り、顔を剃り、化粧をします。
安らかなお顔で眠っているような化粧を施すことにより、生前の故人様になるべく近づけ、ご遺族の悲しい気持ちを和らげる役割もあります。
納棺師の一日の流れ
働く会社やその時の依頼の件数などにもよって大きく変動しますが、ここでは一般的な納棺師の一日の流れについて紹介します。
◆9:00 出社
朝礼後、今日の施行場所や件数を確認して準備に取り掛かります。
<移動>
◆11:00~12:00 現場
1件目の施行をします。
ご遺族と別れた後、車で休憩をとります。
<移動>
◆14:00~15:00 現場
2件目の施行をします。
<移動>
◆16:00~17:00 現場
3件目の施行をします。
基本的には1日に3件前後のことが多いですが、現場間の距離や依頼件数によって幅があります。
◆17:30 帰社
会社に戻り、備品の片付けや翌日の準備、事務作業などを行います。
◆18:00 退勤
以上が、基本的な納棺師の一日の流れです。
ご覧の通り、現場で「納棺の儀」ができる時間は1時間しかない場合が多いです。
納棺師は、1時間という時間制限のなかですべての儀式を終わらせるための技術が必要なのです。
難しいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、おくりびとアカデミーではこういった技術も半年間で学び、即戦力として活躍できるようにお手伝いしています。
日本全国で活躍する納棺師
あくまで目安ではありますが、納棺師は全国に約2,000人程度居ると考えられています。
活躍の場はさまざまですが、約70%が納棺の専門会社、約20%が葬儀社内の納棺部など、約10%は主婦やパートタイマーなどをしながら、フリーランスの納棺師として活躍しているようです。
おくりびとアカデミーでこれまでに卒業した納棺師は約200名以上のため、10人に1人はおくりびとアカデミーで卒業した納棺師と言えるでしょう。
納棺師になるためには?
納棺師になるために必須の国家資格はありません。
ただし、多くは葬儀会社や専門の納棺サービス会社に就職し、現場で経験を積んでいきます。
葬祭ディレクター技能審査やエンバーミングの資格を取得する人もいますが、何より求められるのは「遺族に寄り添う姿勢」と「繊細な気遣い」です。
人の死に直面する仕事であるため、精神的な強さと同時に温かな心を持つことが大切です。
私たちおくりびとアカデミーは、日本で唯一の納棺師育成学校です。
おくりびとアカデミーで卒業した納棺師は、「認定納棺士™」の称号を得ることができます。
そのため、一定の技術や知識が担保されており、安心してお任せいただける納棺師になれるという部分が特徴です。
参加費無料のオープンキャンパスも開催していますので、詳細を知りたい方はぜひご参加ください。
おくりびとアカデミーについて